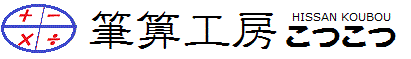デジタル教科書と紙の教科書
今まで補助的に活用されていたデジタル教科書が、正式な教科書として採用されることになりました。
教育現場に新しい器機が導入されると、必ず賛否両論が起こります。
古くは、テープレコーダー、映写機、テレビ、アナライザー、OHP、そして、ビデオカメラ、デジタルカメラ、パソコンルーム、シンセサイザー、CD-ROM、タブレットPC,等々。
やれ、子どもの思考力が低下する、使い方を覚えるのが面倒だ、操作に時間がかかりすぎる、また、高価で学年に一台しか置けない、壊したら大変だから使わない…忙しいのにもう大変。
しかし、学校には次々と新しい器機が導入されてきました。
今はデジタル教科書です。私は紙の教科書と両方を使用すべきだと考えます。指導内容によって使い分けるのが一番です。
その昔、こんなものがあったらいいなあと考えていました。
・仮名文字、漢字の筆順を見せてくれる機械。
・音楽の教科書に載っている楽器の音色を聴かせてくれるボタン。
・円の面積を等積変換して求めている過程のアニメーション。
・拡大図、縮図、回転体などをシームレスに動かして見せてくれるもの。
・割合の問題文を図式化して、視覚的に関係が理解できるもの。
・体育でのそれぞれの身体の動きの動画。
・四則計算の筆算のやりかたの音声付きアニメーション。
・日食や月食の理屈がわかるシミュレーション。
デジタル教科書ならできます。
繰り返しになりますが、領域や単元、指導事項に応じて使い分ける必要があります。
何が何でもデジタルを使うのだという態度が一番よくないです。